
2025年7月の参議院選挙で自民党が歴史的大敗を喫し、石破茂首相の進退と今後の政局が注目を集めている。自民・公明の与党連合は過半数を割り込み、議席数は40程度に留まる見通しだ。この結果を受け、「石破おろし」の動きが加速する一方、首相は続投の意向を表明。衆議院解散の可能性も浮上し、政界は混迷を深めている。本記事では、自民党の惨敗の背景、石破首相の辞任をめぐる議論、解散の可能性、そして世間の反応を徹底的に解説する。
1. 自民党惨敗の背景:なぜここまで議席を失ったのか?
2025年7月20日の参院選で、自民党は39議席、公明党と合わせて47議席にとどまり、過半数(125議席)を大きく下回った。この結果は、2009年の衆院選以来の与党過半数割れとなり、政権運営に深刻な影響を及ぼす。
1-1. 政治とカネ問題の影響
自民党の惨敗の最大の要因は、「政治とカネ」をめぐる不信感だ。2024年の衆院選でも、収支報告書の不記載問題が国民の反発を招き、自民党は191議席に留まった。この問題は参院選でも尾を引き、裏金問題への対応が不十分だったとの批判が続いた。山崎拓元副総裁は「裏金議員への対応が不十分だったことが敗因」と指摘し、70人以上の裏金議員の存在が自民党の信頼を大きく損なったと分析している。
1-2. 物価高と政策の不人気
参院選の主要争点だった物価高対策でも、自民党は野党の消費税減税案に対し、現金給付策を打ち出したが、国民の支持を得られなかった。外国人政策や米国の関税措置、コメ価格高騰への対応も不十分とされ、特に地方での支持離れが顕著だった。鳥取県など石破首相の地元でも、人口流出が止まらず、地方創生の成果が見えないとの不満が広がった。
1-3. 石破首相の求心力低下
石破首相は2024年9月の総裁選で勝利し、10月1日に首相に就任したが、党内基盤の弱さが課題だった。党内では「非主流派」として長年活動してきた石破氏に対し、旧岸田派や麻生派など主流派との溝が埋まらず、党内融和に失敗。2024年10月の衆院選での敗北後、党内から「石破おろし」の声が上がり、参院選の大敗でその動きがさらに加速した。
2. 石破首相の辞任はいつ?続投の可能性は?
自民党の歴史的大敗を受け、石破首相の進退が最大の焦点となっている。世論調査や党内動向から、辞任のタイミングと続投の可能性を探る。
2-1. 辞任を求める声の高まり
2024年11月の衆院選後、毎日新聞の世論調査では「石破首相は辞任すべき」との意見が24%に対し、「辞任の必要はない」が43%だったが、参院選の大敗で風向きが変わった。 X上では、「石破首相は疲れたと漏らした」「自民支持層の5割に見放された」との投稿が相次ぎ、国民の失望感が広がっている。党内でも、森山裕幹事長の責任を問う声とともに、「石破おろし」が本格化する兆しがある。
特に、参院選での自公過半数割れは、石破首相の求心力を決定的に低下させた。Bloombergの報道では、議席数が大幅に減少した場合、政権は正念場を迎え、退陣論が強まるとされている。 また、与党過半数割れなら「退陣不可避」との声も党内から上がり、9月にも総裁選が行われる可能性が浮上している。
2-2. 石破首相の続投宣言とその理由
一方、石破首相は2025年7月20日、FNNの報道によると、辞任せず続投する方針を表明。日米関税交渉など外交上の正念場を理由に挙げ、「国政は一時たりとも停滞できない」と強調した。 2024年10月28日の記者会見でも、「自民党が心底から反省し、生まれ変わる必要がある」と述べ、政権維持に意欲を見せた。
しかし、党内からは「自民が過半数を失い、予算も通せないのに続投は不思議」との批判が噴出。Xでも、「短命政権と言われたくないから居座るだけ」との揶揄が見られる。 国民民主党との連携を模索する動きもあるが、玉木雄一郎代表の不倫報道が影響し、協力関係の構築に不透明感が漂う。
2-3. 辞任のタイミングは?
現時点で石破首相が即時辞任する可能性は低いものの、以下のシナリオが考えられる:
- 9月総裁選での退陣:自民党総裁選が9月に予定されており、党内での責任論が高まれば、石破氏が再選を断念する可能性がある。
- 不信任決議案可決:国会で内閣不信任決議案が可決された場合、憲法の規定により内閣総辞職か衆議院解散が必要。石破首相は「国民の信を問う」と述べており、解散を選ぶ可能性がある。
- 予算案否決:2026年度予算案が否決された場合も、解散の選択肢が浮上。石破氏は「重要な法案が否決されれば国民に判断を仰ぐ」と明言している。


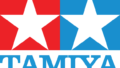
コメント